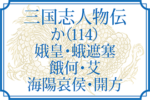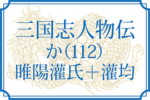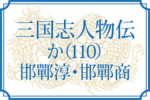正史『三国志』、『三国志演義』に登場する人物たちの略歴、個別の詳細記事、関連記事をご案内する【三国志人物伝】の「お」から始まる人物の一覧㊲、「王」から始まる人物の一覧㊱(王離・王立・王良・王陵・王累)です。
スポンサーリンク
凡例・目次
凡例
後漢〜三国時代にかけての人物は深緑の枠、それ以外の時代の人物で正史『三国志』に名前が登場する人物はオレンジの枠、『三国志演義』にのみ登場する架空の人物は水色の枠で表しています。
目次
スポンサーリンク
お㊲(王㊱)
王(おう)
王離・伯元
生没年不詳。益州・広漢郡の人。『蜀書』楊洪伝が注に引く『益部耆旧伝』に記載がある。
実務の才をもって出世した。督軍従事となったが、法律を公平に執行し、次第に昇進して何祗に代わって犍為太守となり、優れた治績をあげた。
聡明さは何祗に及ばなかったが、文章表現においては彼以上であった。
「王離」の関連記事
王立
生没年不詳。侍中・太史令。
興平2年(195年)、献帝が司隷・弘農郡・弘農県の曹陽澗(渓谷)で敗れた時、船に乗り黄河を東に下ろうと考えた。
この時、侍中・太史令の王立は言った。
「過ぎし春より、太白(金星)が牛斗(牽牛星と北斗星)の辺りで鎮星(土星)を犯し、天津(天の川に横たわる九つの星)を通過しました。熒惑(火星)はまた逆行して北河(双子座の三つの星)にじっと留まっておりまして、犯すことはできません」
その結果献帝は、結局黄河を北方に渡らず、軹関から東に出ようとした。
王立はまた宗正の劉艾に向かって言った。
「先に太白(金星)が天関(星座の名前)でじっと動かず、熒惑(火星)と出会いました。金と火が交わり出会うのは、天命の改まる象です。漢の命運は尽きましょう。晋・魏に興隆する者があるに違いありません」
王立は後にたびたび帝に進言した。
「天命には去就があり、五行は常に栄えるわけではありません。火に代わる者は土、漢を継承する者は魏、天下を安定できるのは曹姓です。一重に曹氏にご委任ください」
曹操はそれを聞くと、人をやって王立に言った。
「公が朝廷に忠義なことは存じているが、しかし天道は深遠である。どうか多言しないでくれ」
「王立」の関連記事
王良
生没年不詳。馬相(軍用馬としての適正を判定するための特徴)を観る名人。名御者。
『蜀書』郤正伝が注に引く王褒(前漢の文人)の『聖主得賢臣頌』(『文選』巻47)に名前が登場する。
「齧膝(名馬の名前)に車を引かせ、乗旦(名馬の名前)をそえ馬とし、王良が手綱を握り、韓哀が同乗するとなると、思いのままに駆け巡っては、あっという間に日の影が消え去るようであり、都を過ぎ国を越えていくのは、土くれを蹴散らすように速い。
走る稲妻を追い、疾風を追い、八方をあまねく巡り、万里の彼方で一休みする。なんとその遙かなことよ。
これも人と馬の呼吸がぴったり合ったからである」
また、『魏書』杜畿伝にある「杜恕の上奏文」と『魏書』管輅伝が注に引く『管輅別伝』にも名前が登場する。
「王良」の関連記事
王陵
生年不詳〜前漢の文帝3年(紀元前177年)。泗水郡・沛県の人。秦末〜前漢の将。
泗水郡・沛県の豪族で、若き日の髙祖(劉邦)は王陵に兄事していた。
沛県で挙兵した劉邦が咸陽に入った当時、数千の兵を集めて南陽郡にいた王陵は劉邦に従ってはいなかったが、その後劉邦が項羽と戦うようになると、王陵は兵を引き連れて劉邦に属した。
すると項羽は、王陵の母を人質にして王陵を従わせようとし、王陵は母に使者を派遣した。
ところが王陵の母は、使者に向かって涙を流しながら「陵(王陵)に伝えておくれ、よく漢王(劉邦)に仕えるように。きっと漢王(劉邦)は天下を手に入れるでしょう。この老母のために二心を持つことのないように。私は死をもって使者を送り出します」と言うと、剣を手にとって自害した。
これに激怒項羽は王陵の母の遺体を煮て辱めた。
結果、王陵は劉邦に従い続け、劉邦によって天下が平定されたが、王陵は劉邦が憎んだ雍歯と仲が良く、また従属したのが遅かったことから、髙祖6年(紀元前201年)になってやっと安国侯に封ぜられた。
王陵は義侠心が強く、直言を好み、前漢の第2代皇帝・恵帝期に右丞相となった。
恵帝が崩御すると、高后(呂太后:恵帝の母)は「呂氏一族を王に封じたい」と思い、朝議に諮った。そこで王陵は、
「髙祖(劉邦)は白馬を生贄に捧げて『劉氏にあらざる者が王となったなら、天下の者は協力してこれを撃つべし』と盟いを立てられました。今、呂氏を王とするのはこの盟いに背くものです」
とこれに反対したが、左丞相・陳平と絳侯・周勃は、
「髙祖(劉邦)は天下を統一すると自分の子弟を王としました。今、太后(呂太后)は称制(皇帝の代行)を行っているのですから、呂氏の子弟を王とすることに、何の問題がありましょう」
と言ったので、呂太后は喜んだ。退出した王陵は陳平らに、
「君たちは『白馬之盟』の場にいなかったのか?今、髙祖(劉邦)は崩御され、呂太后が女主となって呂氏を王に封じようとしている。盟いに背き、どの面下げて地下(あの世)で髙祖(劉邦)に見えるつもりだっ!」
と言ったが、陳平は、
「朝廷で面と向かって争うことでは臣は君にかなわないが、社稷を全うし、劉氏の後継者を定めることでは、君は臣に及ばない」
と答え、王陵は言い返せなかった。
以降、王陵を疎んじるようになった呂太后は、呂后元年(紀元前187年)、形式上、王陵を太傅に栄転させて宰相の実権を奪ったので、王陵は怒り、病気と称して朝議に出席せず、10年後に亡くなった。
『魏書』程昱伝が注に引く徐衆の『(三国)評』に登場する。
「王陵」の関連記事
王累
生年不詳〜建安16年(211年)没*1。益州・広漢郡の人。益州従事。
建安16年(211年)、益州牧・劉璋は別駕・張松の進言に従い、法正を派遣して劉備に益州に来てくれるように頼ませた。
劉璋の主簿の黄権はその利害を述べ立て、従事の王累は自ら州門に身体を逆さ吊りにし、死をもって諫めた*1が、劉璋は聞き入れようとせず、通り道に当たる所に命令を出して劉備をもてなしたので、劉備はまるで自分の国元へ帰還するかのように国境を越えた。
脚注
*1『華陽国志』による。『蜀書』劉璋伝には「自ら州門に身体を逆さ吊りにして諫めた」とあるのみで、その後の生死については触れられていない。
「王累」の関連記事
スポンサーリンク