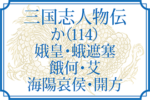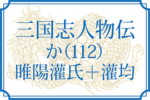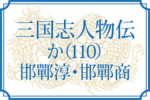正史『三国志』、『三国志演義』に登場する人物たちの略歴、個別の詳細記事、関連記事をご案内する【三国志人物伝】の「い」から始まる人物の一覧④です。
スポンサーリンク
目次
凡例・目次
凡例
後漢〜三国時代にかけての人物は深緑の枠、それ以外の時代の人物で正史『三国志』に名前が登場する人物はオレンジの枠、『三国志演義』にのみ登場する架空の人物は水色の枠で表しています。
目次
韋
倚
尉
猗
懿
育
乙
壱
スポンサーリンク
い④(韋・倚・尉・猗・懿・育・乙・壱)
韋(韋休甫・韋晃)
韋晃
生年不詳〜建安23年(218年)没。司直(諸官府の監察を行う丞相府の属官)。
建安23年(218年)春正月、漢の大医令・吉本、少府・耿紀、(吉本の子:吉邈、吉穆)らと共謀して魏王・曹操に反乱を起こす。
許県で丞相長史・王必の陣営に火を放つが、王必と典農中郎将・厳匡に討伐され、反乱は失敗に終わって処刑された。
「韋晃」の関連記事
倚(倚相)
倚相
生没年不詳。春秋時代、楚の左史(右史と共に天子の側に侍してその言行を記録する官職)。左丘明の祖父。楚の霊王に仕えた。
『三墳』、『五典』、『八索』、『九丘』に精通する。
楚の王孫圉が使者として晋に赴いた時のこと。
晋の定公が開いた宴会の席上で、「楚の白珩*2はまだありますかな?」と問われた王孫圉は、「ございます」と答え、「その宝としての価値はいかほどか?」と問う趙簡子(趙鞅)に、次のように答えた。
「あれは宝とは申しません。楚が宝とするものは、まずは観射父。優れた訓辞を作って諸侯に行き渡らせていますので、寡君*3がそしりを受けることはありません。
また、左史の倚相がいます。彼は百の古典に精通し、一日中寡君*3に過去の良い例と悪い例を示して先王の業績を忘れることがないようにし、また鬼神を喜ばせてその欲悪を正し、楚に神の怨痛が降りかかることを防いでいます。
(中略)
これらが楚国の宝です。かの白珩*2のごとき物は、先王の玩具に過ぎません。どうしてあんなものを宝と申しましょうか」
脚注
*2楚に伝わる宝物。珩とは横長の佩玉(大帯にかける玉製の飾り)のことで、白珩はその純白のもの。
*3他国の人に対して自分の主君をへりくだって使う言葉。
「倚相」の関連記事
スポンサーリンク
尉(尉仇台・尉佗)
尉仇台
生没年不詳。夫余王。
夫余はもともと幽州・玄菟郡に属していたが、後漢末に公孫度が海東の地域に勢力を伸ばして異民族たちを威服させると、夫余王の尉仇台は改めて遼東郡(公孫度)の支配下に入った。
公孫度は、夫余が当時勢いが強かった2つの異民族・句麗(高句麗)と鮮卑の間に位置することから、両国への牽制のため自分の一族の娘を妻として尉仇台に与え、結びつきを強めた。
尉仇台が死ぬと簡位居が王に立った。
「尉仇台」の関連記事
尉佗(尉他、趙佗)
生年不詳〜建元4年(紀元前137年)。冀州・真定国(常山国)・真定県の人。
前漢時代、嶺南(広東省、広西チワン自治区、ベトナムの北部)に独立していた南越国の初代の王[在位:高祖4年(紀元前203年)~建元4年(紀元前137年)]。南越王。武帝を自称する。
秦時代に南海郡・竜川県の県令、南海都尉となり、秦・漢交代期に独立して桂林郡と象郡を合わせて南越を建国した。
高祖11年(紀元前196年)、前漢の高祖(劉邦)は陸賈を派遣して独立を認め、正式に南越王の印綬を送ったが、高祖(劉邦)が崩御すると、呂后は鉄製器具の交易廃止を要求。
これに反発した尉佗(趙佗)は武帝を自称して長沙国に侵入したが、文帝が即位すると再び陸賈が派遣され、「帝号を用いないこと、毎年朝貢すること」などを約束して和睦する。景帝の時代までこの状態は続いたが、南越国内では帝号を用い続けていた。
「尉佗」の関連記事
猗(猗頓)
猗頓
生没年不詳。魯の人。春秋時代末期の富豪。
猗頓は河東(山西省)の塩池で塩を製造して家を起こし、その富は王者に匹敵した。
後世、「陶朱猗頓」と言えば、莫大な富・富豪を指す。陶朱(陶県の朱公)とは、春秋時代末期に越王・勾践に仕えた范蠡のこと。
韋曜が著した賭博を批判する文章・『博奕論』の中で、「もしそれ(博奕に注ぐ労力)を財貨運用の面に用いるならば、猗頓の富が蓄えられよう」と、賭博の無益さの例の1つとして挙げている。
「猗頓」の関連記事
スポンサーリンク
懿(懿公〔衛〕)
懿公〔衛〕
春秋時代、衛の第19代君主(在位:紀元前668年~紀元前660年)。生年不詳〜紀元前660年没。諱は姫赤。父は衛の第16代及び第18代君主・恵公。
紀元前660年12月、衛が北方異民族の翟(狄)に攻撃された際、懿公は翟(狄)を迎撃しようとしたが、懿公が異常なまでに鶴を愛し、淫楽奢侈であったため、みな「鶴に翟(狄)を討たせたらよろしい」と言って従わなかった。
そこで懿公は自ら出陣するも、敵の集中射撃を浴びて戦死。その屍は翟人(狄人)に食われ、ただ肝臓だけが残ったと言う。
大切にすべきものを軽く扱い、くだらないものを大切にしたために身を滅ぼすことのたとえ、「懿公好鶴」の語源となった。
「懿公〔衛〕」の関連記事
育(育延)
育延
生没年不詳。鮮卑の豪族。常に幷州(并州)の人々に恐れ憚られていた。
ある朝、育延は部落民5千余騎を引き連れて幷州刺史・梁習に商取引を求めた。梁習は「受けなければ怨みを買い、受けても略奪をうけることになる」と思ったが、結局これを承諾する。
交易が始まると、市場管理の役人が1人の蛮人を捕縛した。育延の騎兵はみな驚いて、梁習を幾重にも包囲して弓を引きしぼったが、蛮人を捕縛した理由を聞いてみると、蛮人に非があったことが分かった。
そこで梁習は育延を呼び、「お前たち蛮人が自分から法を犯したのだ。役人はお前に害を与えたわけではないのに、どうして騎兵たちを使って人を驚かせるのだ」と言って、彼を斬ってしまった。
「育延」の関連記事
乙(乙修)
乙修
生没年不詳。正始2年(241年)に呉の朱然が樊城を包囲した際の魏の守将。
この時救援に駆けつけた夏侯儒は、樊城の東の鄧塞に駐屯したものの、兵が少ないためにそれ以上進むことができず、ただ太鼓や笛を鳴らして気勢を上げることを繰り返すだけだった。
乙修らは城内からその様子を眺めるだけだったが、一月余りして太傅の司馬懿が到着すると、朱然らは逃走した。
「乙修」の関連記事
壱(壱多雑)
壱多雑
生没年不詳。西域(東トルキスタン)にある車師後王国*4の王。車師後部王。
魏の王朝は壱多雑に守魏侍中の官職を与え、大都尉の称号を送り、「魏王(親魏王?)」の印章を授けた。
脚注
*4シルクロード(北の新道)に点在する東且弥国、西且弥国、単桓国、畢陸国、蒲陸国、烏貪国が服属し、宮廷は于頼城にある。
「壱多雑」の関連記事
スポンサーリンク